


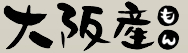

伝統を継承し文久三年(1863年)創業・・・・鶴屋八幡の技法は、約320年前の元禄時代まで遡ります。元禄15年(1702)創業で、江戸時代の天下の台所と言われた上方で高名であった、老舗菓子店 虎屋伊織が起源になります。正確には、虎屋大和大掾藤原伊織(とらややまとだいじょうふじわらのいおり)と言い、店の間口は六、七間もあり、その隆盛ぶりは『東海道中膝栗毛』にも登場します。江戸時代の商人番付にも度々登場し、幕末まで九代に亙り繁盛しましたが、 九代目当主 竹田七郎兵衛が病弱のうえ実子が無く、そこへ動乱期の世情不安 が重なり、160年続いた老舗も商いが行き詰まりました。

困ったのは、大坂のお茶人達でした。 当時は饅頭が有名でしたが、お茶席用の上生菓子が主力でその数800種程あり、大阪城にも記録が残り、大名や鴻池家等の豪商、お茶人など顧客それぞれのお好みも心得ておりました。

そこで幼少の頃より縁あって奉公し、主人より厚い信頼を得ていた今中伊八が、お茶人や贔屓筋と九代目当主から「このままでは、連綿と受け継いだ我家製法が、途絶えるのは忍びない。幸い、そなたは幼少の頃より奉公し我家製法を修得し顧客の信頼も厚い。以って別に居を構え我家製法を後の世に守り伝えなさい」(初代の書き残した「虎屋大和大掾藤原伊織由来略伝」より)との有難い仰せがありました。 また、主家に原料を収めていた八幡屋辰邨からの「商売の見通しが立つ迄、心置きなく材料を使ってよいから」との願ってもない後押しもあり、伝統の火を消すまいと、虎屋伊織の職人達と製法、技術を踏襲し、文久3年(1863)に同じ高麗橋に心機一転、鶴屋八幡として暖簾を掲げました。


あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
わ